皆さんは自分たちがもらう年金についてご存じでしょうか?
お恥ずかしながら、私は社会人になってもまだ自分には関係ない話として年金についてはろくに調べず今まで過ごしてきました…
しかし、資産運用をしていく中で、年金について理解を深めることは重要である思い、今回年金について記事を作成することにしました。もし、私と同じように年金についてよく知らない方のお役に立てたら幸いです。
今回の記事においては年金の仕組みから具体的な受給金額まで調査しました。
Contents
サラリーマンの年金の仕組みとは
年金制度は強制加入の公的年金と、任意加入の私的年金があります。
それぞれの特徴について見ていきましょう。
公的年金
公的年金の基礎にあるのは、国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全国民が対象となる国民年金(基礎年金)です。これに更にサラリーマンや公務員は厚生年金があります。
国民年金、厚生年金に共通するのが以下の点です。
繰下げ受給の場合、繰り上げた月数×0.5%が年金金額から減額 繰上げ受給の場合、繰り上げた月数×0.7%が年金金額から増額
被保険者が亡くなるまでの間、年金受取人が一生涯年金を受け取ることができる
私的年金
私的年金とは公的年金に上乗せする制度です。
主に、確定給付企業年金制度(DB)、企業型/個人型(iDeco)がある確定拠出年金制度(DC)等があります。
私的年金は任意加入と言いつつ、会社が上記仕組みを採用していたら、気づかないうちに加入していますね…
その他
年金制度ではありませんが、少額非課税制度として、NISAや積立NISAがあります。
私的年金やNISA、積立NISAは各個人の状況によるため、次項からは公的年金(国民年金、厚生年金)に着目していきます
サラリーマンの公的年金でもらえる金額イメージ
国民年金、厚生年金
以下厚生労働省の調査資料を参照しました。
国民年金:約5.6万円/月
厚生年金:約14.4万円/月
厚生年金は以下数式にて算出できますので、より実体に近い金額算出をしたい場合はご参考にどうぞ。
=(平均年収/12か月)×5.481/1000×月数(12か月×加入年数)=平均年収×0.005481×年数
繰下げ受給について
次に国民年金、厚生年金を繰下げ受給した場合について見ていきます。
繰下げ受給とは、原則65歳から受給できる年金を66~70歳まで後ろ倒しすることによって、増額して年金を受給できる仕組みです。
70歳から受給した場合、65歳時点の月額金額×1.42倍となります。上述した平均月額を例にとると以下の通りです。
国民年金:約5.6万円/月⇒約7.9万円/月、厚生年金:約14.4万円/月⇒約20.4万円/月

また、ご自身の年金受給を詳細に把握したい場合以下サイトをお勧めします。
ざっくりとしたシミュレーションをしたい場合に非常に便利です。
これまで自分の納付してきた記録をベースによりご自身にあった年金見込み金額のシミュレーションが可能です(繰上げ、繰下げ受給を含)。
ただシミュレーションにおいてはユーザーIDが必要となりますが、年金手帳番号を入力し申し込めば、1~2週間程でユーザーID登録が完了しますので、自分の年金見込み金額シミュレーションを実施したいという方には登録することをお勧めします‼
老後の生活支出について
これまで老後に貰える年金受給額について見てきました。
一方で、老後にいくら生活費が必要なのか調べる為以下を参照しました。

生活保障に関する調査によると、夫婦二人で老後生活を送る上で必要と考えられている最低日常生活費は以下の通りです。
最低日常生活費:22.1万円/月
経済的にゆとりある老後生活費用として、上記以外に以下金額の上乗せが必要と考えられています。
上乗せ額:14.0万円/月
まとめると、夫婦二人で最低限生活を送るには、22万円/月必要で、経済的にゆとりある生活をするには、36.1万円/月必要ということになります。
ただ、これらについては調査自体がアンケートがあり、かなり大雑把な数字ではないかなと印象を持ちましたが、一つの指標として考えることとしました。
まとめ
これまでの状況をまとめると以下の通りです。
国民年金 約6万円/月
厚生年金 約14万円/月
最低限の生活費: 22.1万円/月
経済的にゆとりある生活費: 36.1万円/月
このシミュレーション結果から、ゆとりある生活費に及ばないが、妻と二人分の公的年金を考慮すれば、何とかやっていけそうだなと感じました。
また、支出に関しては自分で選択できるものなので、調整して下げることも可能かなと思いました。
考慮すべきリスク
これらのシミュレーションは更に考慮すべきリスクとして長生きするリスクがあります。医療技術の発展により、巷では人生100年論が話題になっております。
長生きすることによって、事故に遭ったり、介護が必要となる可能性も出てきます。
もし仮に老後になって上記リスクに遭遇した場合、先を見通せず、働ける時間も限られ非常に厳しい状況に陥ることが想定されます。
解決策
このリスクに対して以下対策が有効と言えます。
配当金によるキャッシュフローの最大化
65-69歳までの生活費用は退職金、貯金、および、資産の一部切り崩しで対応
国民年金、厚生年金の終身年金特性を生かし、繰下げ受給による公的年金の最大化を図る
貯金や資産の切り崩しではいつなくなるかわからない恐怖がある為、配当金や年金の不労所得の最大化を図ることで長生きするリスクに対しても備えていくことが今後のポイントとなるでしょう。
少しでも読んでいただいた方々に役に立てたら嬉しいです。
ではまた‼
”歩いた道こそ武勇伝”
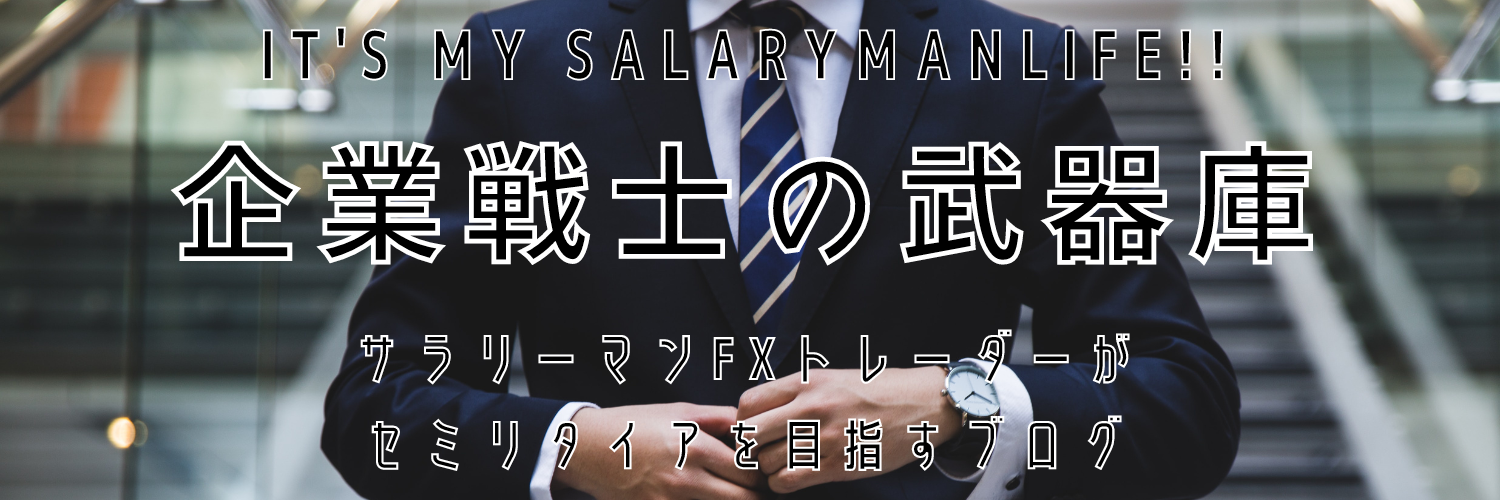



コメント